全国の体育教師のためのサイト”さとし”

部活動の指導方法、トレーニング方法、指導案、保健の小話
さとしを読めば、スムーズに指導できます。
人気記事
キーワードから記事検索も可能です
カテゴリー
指導案
見たい指導案の項目をタップしてください!
トレーニング・上達法
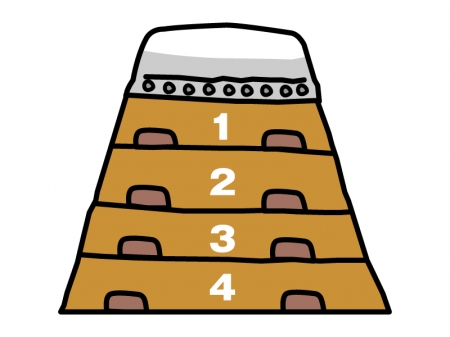
ゼロから始める跳び箱入門①道具の準備の仕方
2018.06.122022.03.01
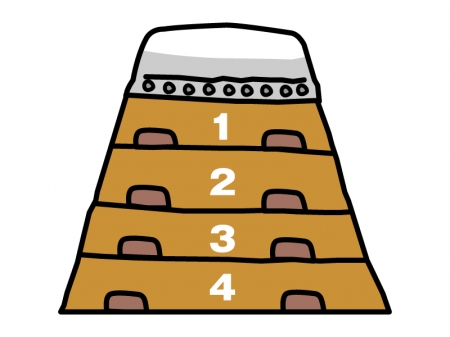
ゼロから始める跳び箱入門③ウォーミングアップ
2018.06.072022.03.01

他人には教えたくない鉄棒上達の秘訣④空中逆上がり
2018.05.142022.03.25
部活動指導

部活中に起きやすい怪我と対処法⑪ボート・カヌー
2018.06.072022.03.01

部活中に起きやすい怪我と対処法⑩陸上走り幅跳び
2018.06.072022.03.01

部活中に起きやすい怪我と対処法③バスケットボール
2018.05.132022.02.28









